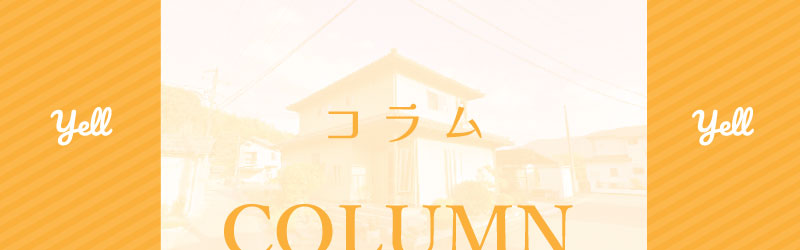
②【在宅支援】てまったく通わなくていいの?

答え:いえいえ!実はいくつかルールがあるんです!
① 在宅支援を行うための基本条件
在宅支援は、コロナ禍以降に認められた「例外的な形態」から、現在では正式な支援方法として位置づけられていますが、
原則は通所が基本であり、在宅で行う場合は次のような条件を満たす必要があります。名前が紛らわしいかもしれませんね。
〇利用者本人の体調や障害特性、家庭の事情等により「通所が困難」な状況があること。
〇支援計画(個別支援計画)に、在宅での支援内容・方法・頻度を明確に記載していること。
〇行政(指定権者=市町村)の確認・承認を得ていること。
事業所と利用者様とのやり取り
② 定期的な連絡・コミュニケーションの確保
在宅で作業を行う場合でも、事業所は「通所しているのと同等の支援」を行う責任があります。
したがって、定期的なコミュニケーションが必須です。
〇原則:毎日1回以上、電話・ビデオ通話・メール・チャット等で「連絡・確認」を行う。
〇その内容を記録(支援記録・業務日誌等)に残す。
〇利用者様が体調を崩したり、作業に支障が出ていないかなど、安否確認・健康状態の確認も含めて行う。
〇状況に応じてオンライン面談(ZoomやLINE通話など)を実施してもよい。
③ 作業した資材のやり取り
在宅支援では、作業をどのように受け渡し・回収するかも決まっています。
〇作業キット・材料などは職員が自宅に届ける、または事業所での受け渡しを行う。
〇完成品は職員が回収し、内容確認を行う。
〇作業の進捗確認や品質チェックを、ビデオ・写真送付・チャット報告などで行うことも可能。
④ 支援記録と報告義務
〇毎日の支援内容(連絡の有無、作業量、体調、支援方法など)を支援記録に残す必要があります。
〇行政からの実地指導では、「在宅支援の記録」が求められるため、事業所は記録が残る形でやり取りを保存します。
〇例:LINEでのやりとりのスクリーンショット、メール履歴、支援報告書 など。
⑤ 在宅支援の頻度・支援時間の考え方
〇原則として、「1日あたりの支援時間」が明確に設定されている必要があります。
(例:9:30~15:30のうち、作業・休憩・支援を含む時間)
〇1日の作業時間を大幅に下回るような支援内容の場合は、報酬請求上の対象外となることがあります。
〇定期的に(少なくとも月1回以上)通所日や面談日を設け、事業所での支援・評価・今後の計画を行うのが望ましいとされています。
【エール万富の取り組み】
エール万富では、在宅支援を希望される利用者の方に対して、
毎日の健康確認・作業状況の報告をLINEやメール、電話連絡で行い、週1回はビデオ面談(ZOOM・LINE)を実施しています。
また、職員がご自宅まで材料の受け渡しに伺い、作業の進捗を一緒に確認します。
「通えない日も、つながりは絶やさない」ことを大切にしています。
少しずつでいい。毎日通えるようになる日を目指して一緒に始めませんか?

